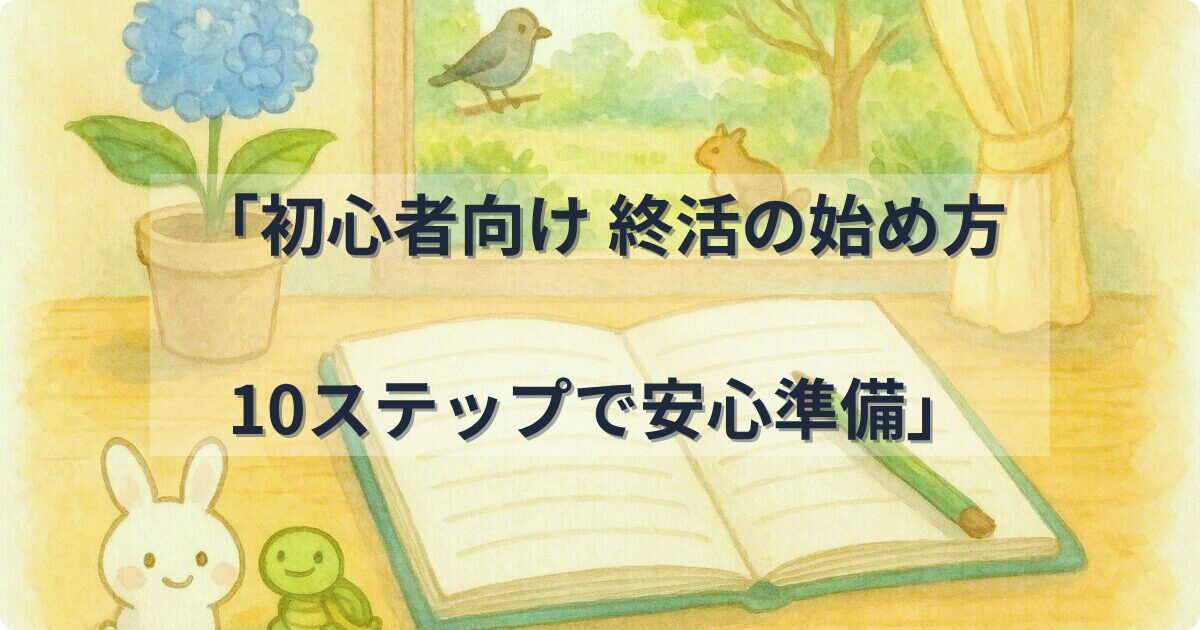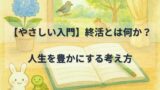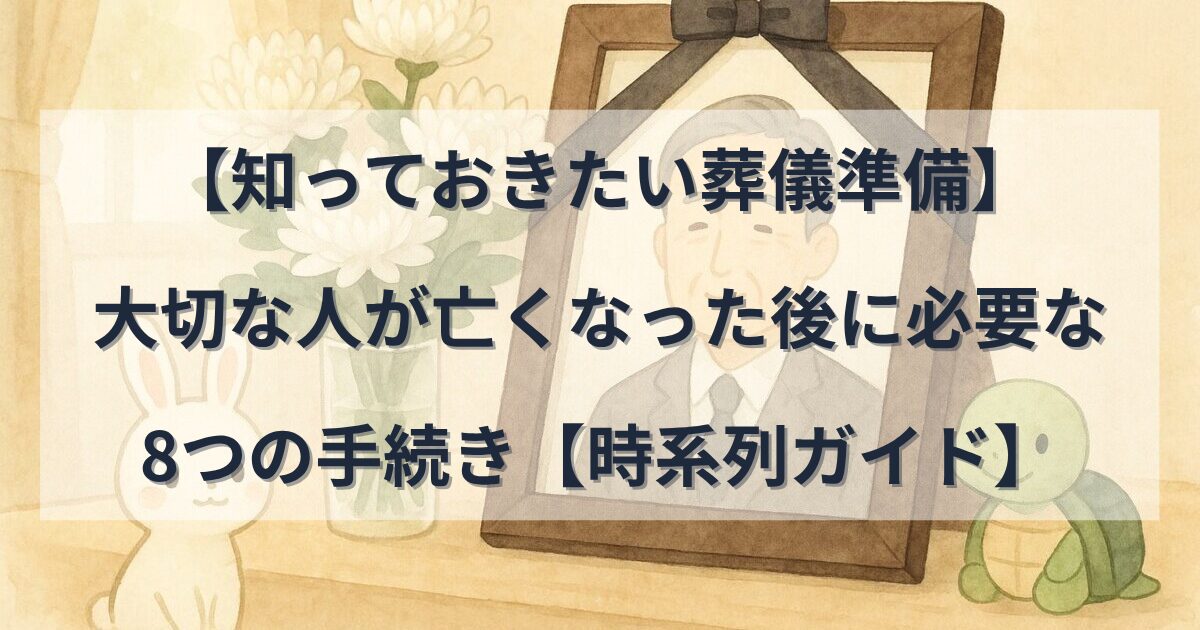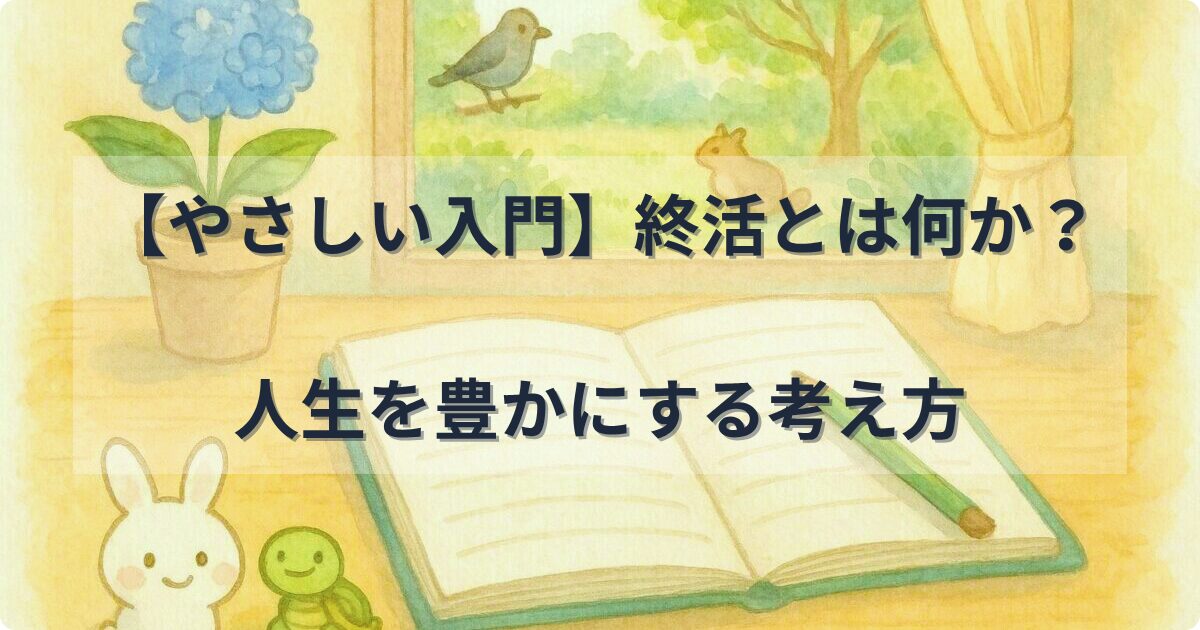✅はじめに:終活って、なんだか難しそう…?
こんにちは。「ここからの私(終活Life)」のたけはるです。この記事を読むと、「終活 始め方」や「初心者 終活」といったテーマに悩む方でも、終活の全体像がやさしくつかめるようになります。
長い構成になっていますが、これを読めば「終活の始め方」がどういうものか大体わかります。ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。
終活って何だろう?と思う方は前の記事もぜひ読んでみてください。
この記事では、初心者の方にもやさしい10のステップをご紹介します。
ステップ① 終活は“話すこと”から始めよう
終活は、1人で抱え込まずに「家族と共有すること」から始めるのがおすすめです。
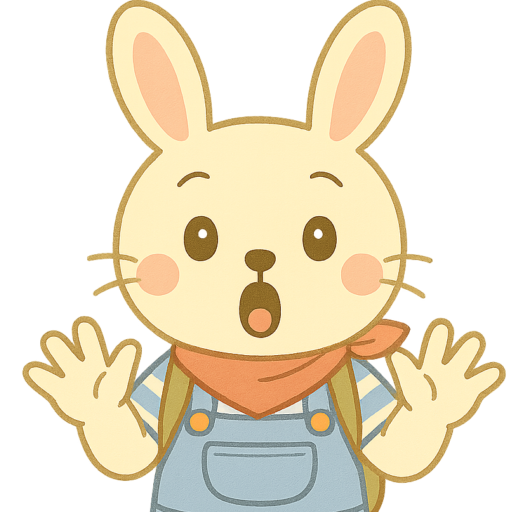
終活って1人で考えるものでしょ? 家族に話したら心配されない?

ううん、話しておくことで“安心”が生まれるんだよ〜。自分の希望や気持ちを伝えることは、大切な準備のひとつだよ
🗣 話題のきっかけにぴったりな言葉たち
🔷終活を始める側からの言葉
- 「最近、これからの暮らし方をちょっと考えててね」
- 「私が元気なうちに、ちゃんと伝えておきたいことがあるの」
- 「家族に迷惑かけないように、できることから整えておきたいなって」
🔷支える側からの言葉
- 「もしもの時、どんなふうにしてほしいかって考えたことある?」
- 「何か困った時に備えて、知っておきたいことあるかな?」
- 「最近“終活ノート”っていうのがあるらしいけど、気になる?」
📝会話のポイント
大切なのは、結論を急いで“重たい話”を一気に片づけることではなく、いつもの世間話の輪の中にそっと終活の種をまくことです。
たとえば――「もしものとき、写真はどこにまとめておこうか」「私が好きな曲、最後に流してもらえたらうれしいな」――そんなさりげない一言が、深呼吸するように心を開き、終活への扉を静かに開いてくれます。
その何気ない一言が、あなたと大切な人たちの心に柔らかな灯をともす――それが終活の、本当の始まりなのです。

雑談の延長で、“もしもの時どうしたい?”と聞いてみるだけでも大きな一歩になるよ
ステップ② エンディングノートで想いをまとめる
エンディングノートは、思いを文字にすることで気持ちの整理ができるツールです。書く内容は自由ですが、よくある項目は以下のようなものです
- 自分のプロフィール・大切な思い出
- 連絡先・資産・医療の希望
- 葬儀や供養の考え方
- 家族や大切な人へのメッセージ
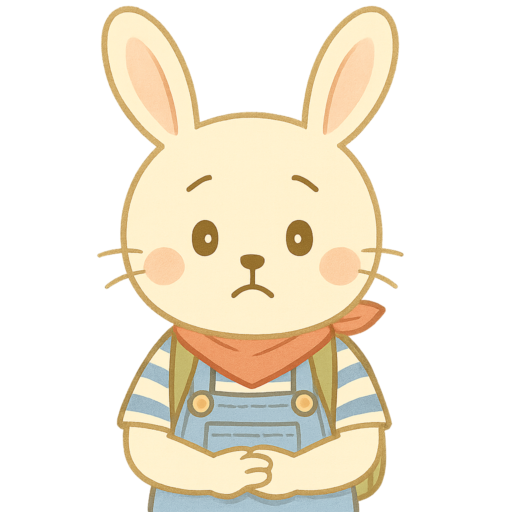
でも…全部書くの大変そうだよ〜
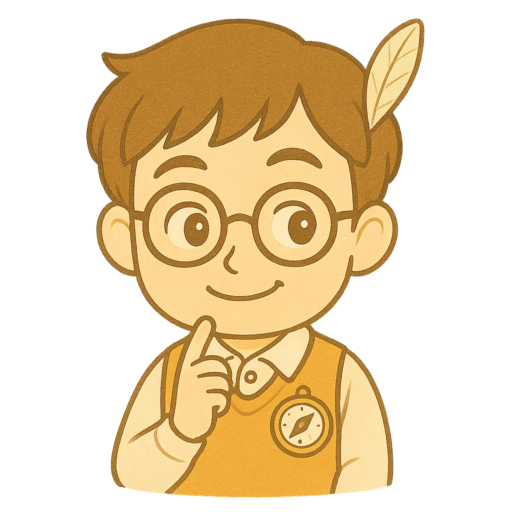
大丈夫。最初は“今の気持ち”を1行だけ書いてみよう。それだけでも意味があるよ
紙のノートにこだわらず、スマホのメモアプリやパソコンのワード、音声入力など、好きな方法で「エンディングノート」を始められます。最近は多くの市区町村が無料で配布するPDFテンプレートもあるので、必要な項目だけ印刷して使ったり、直接タイピングして保存したりするのもおすすめです。

きれいに書こうと構えなくていいんだよ~。自分らしく書くのが一番大切かもね
このステップで目指すのは、“完璧に仕上げること”ではなく、“書き始めること”です。思い出したときに一行だけメモする、ボイスメモにひと言残す――そんな小さな一歩が、未来の自分や家族への大きな贈り物になります。
ステップ③ 財産・口座の“見える化”をしよう
終活でつまずきやすいのが「お金や資産」の話。でも実は、家族にとって一番ありがたい準備でもあります。
チェックしておきたい主な項目
- 預貯金(通帳やネットバンク)
- 保険(生命保険・医療保険など)
- 年金・証券・投資信託
- 不動産(土地・家屋)
- ローンや借金の有無

持ち物リストだけじゃなくて、『どこにあるか』『どう管理しているか』まで書いておくと、もっと安心かもね〜

じゃあまずは通帳と保険証の保管場所をメモしてみるよ〜
重要なのは、単に「何を持っているか」を羅列するだけではなく、その資産が「どこにあるのか」「どのように管理しているのか」まで一緒に記録することです。
例えば、自宅の金庫に現金を入れているならその場所と開け方、証券会社に預けている有価証券なら口座番号やログイン方法、保険証券ならファイルの名前やファイリングのルールなどをメモしておくと、いざというときに家族がスムーズに手続きを進められます。
実際にこのような記録が役立った事例もあります。
「母が急に倒れたとき、どの保険に入っているか家族が把握できず手続きに手間取りました。今は財産管理ノートにまとめてくれているので、必要書類をすぐに見つけられてとても助かりました」(50代・男性)
このステップでのゴールは、“すべてを完璧にまとめる”ことではなく、“まずは記録を始める”こと。通帳の残高チェックをメモする、保険証の保管場所を書き留める――そんな小さな一歩でも、「見える化」を進めることで家族の安心感は大きく高まります。
ステップ④ 書類整理で“いざという時”に備える
「遺言なんてまだ早い」と思っている方も多いですが、実は元気なうちにこそ考えておきたい大切な準備です。ここでは代表的な遺言や贈与の基本を簡単にお話しします。
遺言には大きく分けて以下の2種類があります。
- 自筆証書遺言:自分で書く。法務局で保管できる制度あり
- 公正証書遺言:公証役場で作成。費用はかかるが確実性が高い
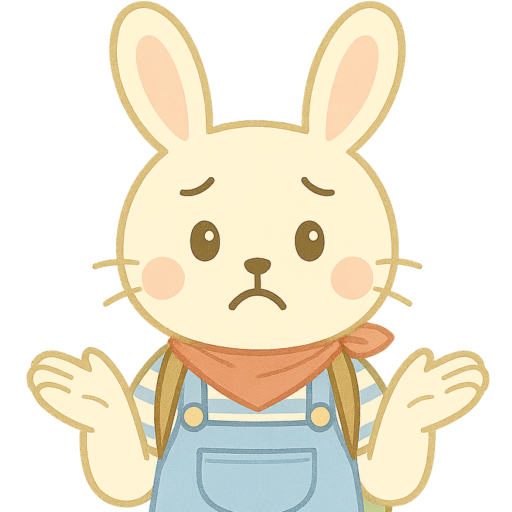
どっちにしたらいいのか、よくわからないよ〜
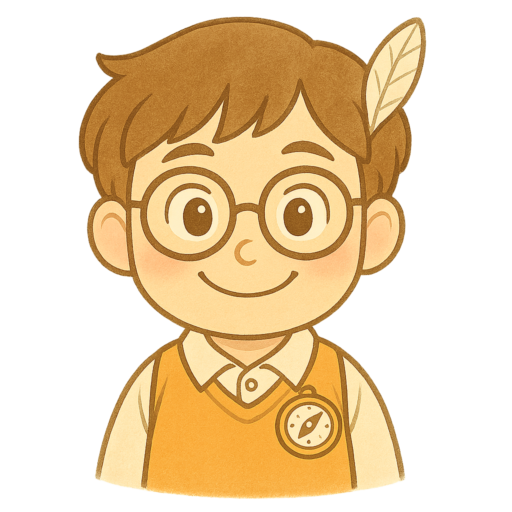
迷ったら“公正証書遺言”が安心かな。でも、まずは“書いてみる”ことが大事だよ
また、生前贈与という方法もあります。生前贈与は、相続を待たずに元気なうちに財産を移転できる仕組みです。贈与税には基礎控除として年間110万円まで非課税になる制度がありますが、同一の相手へ継続的・定期的に渡すと「定期贈与」と判断され、まとめて課税されるリスクがあります。
そのため、贈与のタイミングや金額、方法には注意が必要です。どのくらいを、いつ、どのように渡すかはケースバイケース。手続きの正確さや最適なプランを考えるには、税理士など専門家への相談がおすすめです。

遺言は“争族”を防ぐための“思いやりの手紙”でもあるんだね〜
ステップ⑤ 遺言と生前贈与で“想い”を残す
モノの整理は、心の整理にもつながります。
まずは以下のように分類してみましょう・
- よく使うもの
- 使っていないけど残しておきたいもの
- 使っておらず、処分を検討してもいいもの
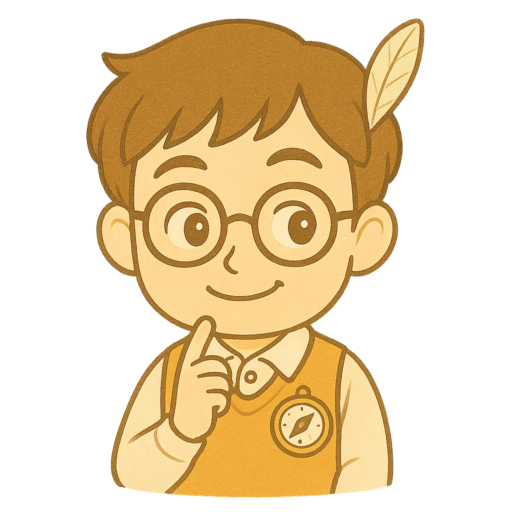
迷ったら“残す理由”を自分に問いかけてみよう。“ありがとう”と心の中で声をかけて手放すのも一つの方法だよ
また、写真はデジタル化する、手紙はまとめて1冊に保存するなど、形を変えて残す工夫も有効です。
写真はスキャナーやスマホアプリでサクッとデジタル化し、手紙やカードはまとめて1冊のスクラップブックやファイルに保存すると、場所を取らずに大切な思い出を残せます。
具体的には以下の方法がおすすめです。
写真のデジタル化
- アプリで一括スキャンしてクラウドに保存
- 年ごとやイベントごとにフォルダ分けすると検索しやすい
手紙・カードのまとめ方
- サイズをそろえてアルバムに貼り付け
- 透明ポケット付きバインダーを使うと出し入れも簡単
このステップのゴールは、“全部を一気に整理する”ことではなく、“まずは一か所だけ手をつけてみる”こと。小さな引き出しひとつから始めるだけでも、思い出の見える化が進み、日々の暮らしがぐっとすっきり感じられるはずです。

部屋が整うと、こころもふわっと軽くなるよ〜
ステップ⑥写真や手紙を整理して心も軽く
「終活って、やっぱりお葬式やお墓のことを決めるんでしょ?」そんなイメージを持つ方も多いかもしれません。
終活のイメージは「お葬式やお墓をどうするか」だけに偏りがちですが、本質は“残される家族が困らないように安心を残す”ことです。選択肢も昔より多彩になっており、それぞれの希望を自由に組み合わせられます。
🕊葬儀のスタイル例
- 家族葬:親しい家族・親戚だけで静かに行う
- 直葬(火葬式):告別式を行わず火葬のみ実施
- 一日葬:告別式と火葬を同日中にまとめる簡易型
- オンライン葬:遠方の親戚・友人が参加できる配信型
🕊お墓の例
- 永代供養:寺院や霊園が管理を代行
- 樹木葬:樹木や植栽の下に納骨
- 納骨堂:屋内のロッカー式納骨施設
- 無縁墓なしプラン:お墓を持たず供養のみ依頼
これらを“迷わずに見つけられるかたち”で残しておくことで、葬儀社や親族への連絡・手続きがスムーズになり、家族の負担を大きく軽減できます。
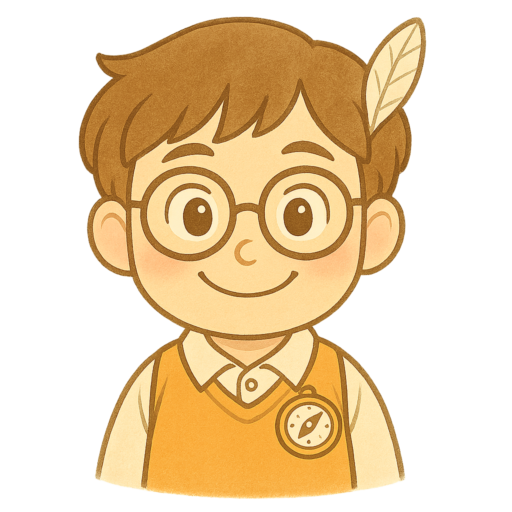
迷わせない”準備こそが、何よりの愛情だよね

書いておくだけで、心がずっと軽くなった気がする〜
ステップ⑦ “葬儀と供養”の希望をメモしておこう
「もしもの時、どんな治療を受けたいか」「どこで過ごしたいか」―そんなことを、元気なうちに考えておくことも、終活の大事なステップのひとつです。

まだ元気なのに、そんな先のこと考えるのってちょっと…
――でも、“もしものとき”の希望を元気なうちに整理しておくことは、自分自身も家族も安心できる大切なステップです。以下のポイントを参考に、書き出してみましょう。
治療の選択肢をイメージする
- 延命治療を希望するかどうか
- 緩和ケア(痛みを和らげるケア)を優先するか
過ごす場所の希望を具体化する
- 最期は慣れ親しんだ自宅で過ごしたい
- 病院やホスピスで専門家に看護してほしい
- 親しい人と集まれる施設を選びたい
選択肢をリスト化して、優先順位をつけると、後で家族が判断しやすくなります。
共有の方法を決める
- 書面(エンディングノートやACPシート)に残す
- 家族やかかりつけ医と面談を設ける
- 画像や音声メモで「声」を残す
💬ポイントは「今の気持ち」でOK
これらを“難しく考えすぎず”、日常のすき間時間に一言ずつ書き足していくことがポイント。書き始めたときの気持ちが、そのまま「あなたらしさ」として家族に伝わります。まずはノートやアプリに「延命治療は望まない」「自宅で穏やかに過ごしたい」と一行だけ書いてみましょう。それが、未来への安心を形にする第一歩です。

少しずつ考えて、書き足していけばいいんだね〜
ステップ⑧ “住まいと暮らし”を考え直す
「この家にずっと住み続けるのかな…」
ふとしたときに感じるその思いも、終活の大切なスタートポイントです。
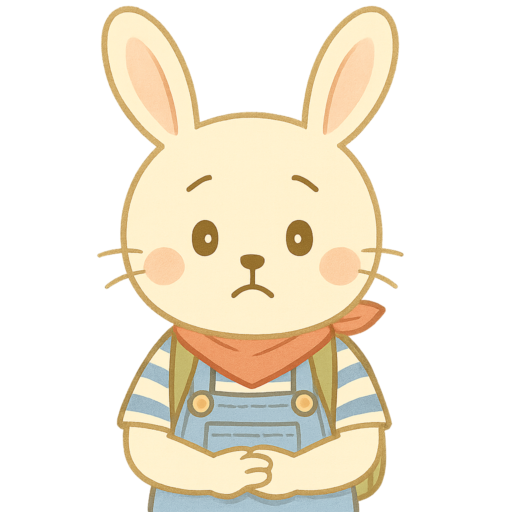
慣れた家だけど、最近階段が辛く感じるんだよね〜
家にずっと住み続けるかどうかは、住まいだけでなく家族との関係性も一緒に考えるチャンスです。
以下のポイントをきっかけに、家族と対話してみましょう。
- 同居・近居の可能性
子どもや親と一緒に暮らすことで、お互いに助け合える距離感を探る - 将来の介護のしやすさ
バリアフリー化や手すりの設置で安心度アップ - 高齢者向け住宅・施設への住み替え検討
サービス付き高齢者住宅やグループホームなど、選択肢を知る - リフォームや改築の検討
段差解消、広めの通路、シニア向け設備導入などで快適さを追求
住まいの見直しは、自分の身体や気持ちに寄り添うこと。そして何より、家族と「どう暮らしたいか」を共有することが、安心の第一歩になります。
思い切って手放すのも一つの手
不動産は大きな財産でもあります。使わなくなる実家や遊休地、名義や相続の整理などを早めに話し合っておくことで、将来の遺族間トラブルや手続きの手間をぐっと減らせます。具体的には
- 空き家になるかもしれない実家の管理・活用方法
- 使っていない土地や駐車場の運用(売却・賃貸など)
- 名義変更や相続手続きに必要な書類・期限の確認

“家のこと”ってちょっと重いけど、みんなの気持ちを聞くだけならできるかも〜
まずは「どんな選択肢があるか」「家族はどう感じているか」を共有することが第一歩。小さな対話が、後悔のない住まいの形をつくる大きな安心につながります。
ステップ⑨“デジタル遺品”の準備も忘れずに
目に見えない資産──スマホの写真や動画、パスワード情報、SNSのアカウント、ネット銀行のログイン情報など──をまとめずに放っておくと、これも立派な「デジタル遺品」になります。形あるものは整理していても、デジタル上の記録はつい後回しにしがち。いざというときに家族がアクセスできないと、大切な思い出や重要な手続き情報を取り出せずに困ることになります。

スマホもパソコンも、気づくと大事なデータがいっぱいだよね〜
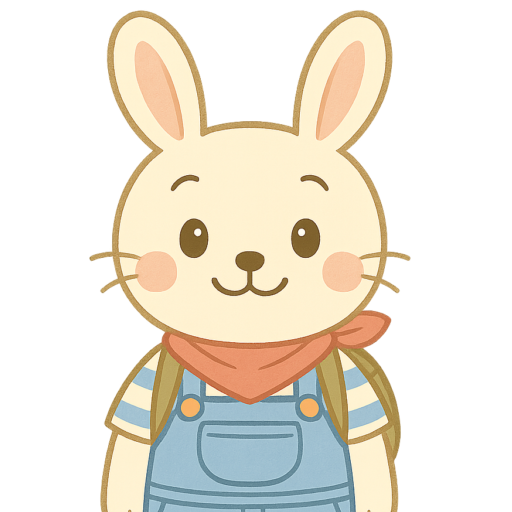
IDやパスワード、どこに書いたか自分でもあいまいかも…!
🧩まずは「どこに何を書いてあるか」「解除や再設定の方法」を、口頭だけでなくメモにも残しておくことから始めましょう。そうするだけで、家族は「スマホが壊れた」「パスワードを忘れた」といったトラブル時にも、迅速に必要な情報にたどり着けます。
📝やっておくと安心な4つのこと
- 利用中サービスのリスト化(SNS・ネット銀行・サブスク)
- パスワードを紙にまとめ、「ここにあるよ」と家族に知らせる
- スマホ・PCのロック解除手順をメモに残す
- 月額課金・サブスク一覧を作り、不要なものは解約しやすく
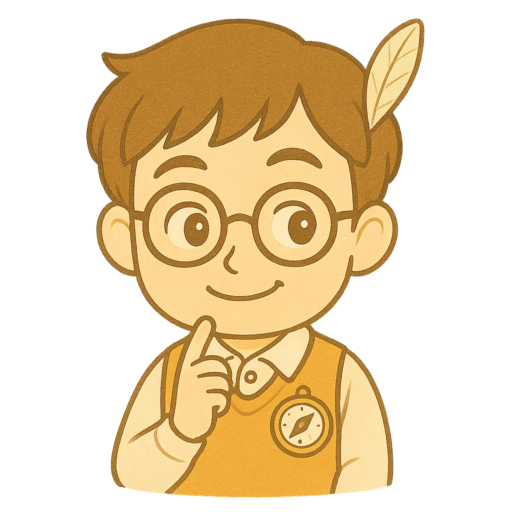
最近はクラウド保存や自動課金が知らず知らず続いちゃうから、書き出すだけでも大きな準備になるよ
実際、「父のスマホが数回の誤入力でロックされ、中の写真や連絡先が見られなくて困った」という声もあります。銀行アプリなどは数回の誤入力でセキュリティロックがかかり、解除に数日かかることもあるため早めの共有が大切です。
このステップは完璧を目指す必要はありません。小さなメモ一枚でも、「デジタルの見える化」ができているだけで、家族の安心度はぐっと高まります。まずはスマホの「重要フォルダ」やネット銀行の「お気に入りサイト一覧」を書き出すところから始めてみてくださいね。
ステップ⑩ 連絡先リストで“想いを伝える”準備を
終活の最後に、大切にしたいのが「人とのつながり」です。これまでの人生で関わってきた友人や知人、感謝を伝えたい人たち。そのひとり一人を思い出しながら、連絡先リストを整えておくことは、未来の安心にも、自分自身の“心の整理”にもつながります。
便利という理由もあり全てをスマホに残しておく人が多いです。家族や友人の連絡先はスマホだけに頼ると、いざというときアクセスできずに困ることがあります。
紙のリストにまとめておくだけで、家族は迅速に連絡を取りやすくなり、不安がぐっと減ります。
まずは大切なつながりを“見える化”することから始めましょう。

連絡先って、スマホにしか入ってなかったりするから、紙に残すのも安心だよ〜
たとえば、こんな情報をリストにしておくと役立ちます。
- 名前と関係性(友人・職場の同僚・ご近所さんなど)
- 電話番号・メールアドレス・住所
- 万一のときに連絡してほしい人や、伝えてほしいメッセージ
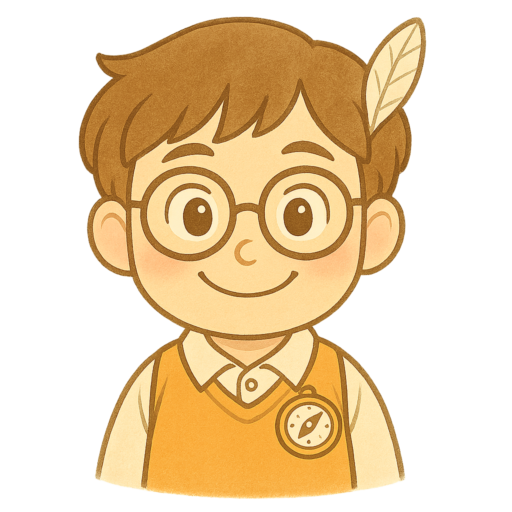
この人には連絡してほしいな”“この人にはお礼を伝えておきたいな”って考える時間が、自分の人生を振り返る大切なひとときになるんだよ
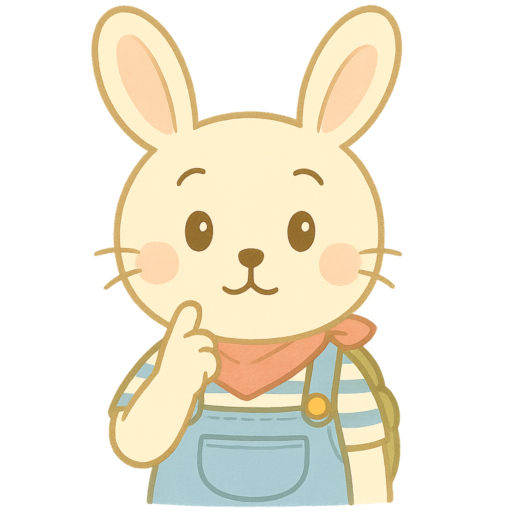
“ありがとう”って言いたい人、けっこういるかも〜。思い出してたら、心がぽかぽかしてきたよ〜
この連絡先リストは、残された家族にとって「誰にどう連絡すればいいか」が一目でわかる心強いガイドになります。そして何より、この作業を通して感じる“ありがとう”の気持ちが、あなた自身の心を軽くしてくれるはずです。
まとめ:今日の一歩が、明日を軽くする
終活とは「何かを終える準備」ではなく、「これからを心地よく生きるための整理」です。
10ステップすべてを一度にやる必要はありません。できるところから少しずつ、自分のペースで進めていきましょう。

今日のあなたの小さな一歩が、明日の安心につながるよ。無理なく、楽しく、終活を始めてみよう!
📝まずはここから!終活ToDoリスト(今日からできる3つ)
- 家族と「将来どうしたいか」を5分だけ話してみる
小さな会話が、安心の土台をつくります。 - ノートに「やっておきたいこと」を1つだけ書いてみる
何を書くか迷ったら、“ありがとうを伝えたい相手”でもOK。 - 通帳・保険証など大事なものを1カ所にまとめる
「どこにあるか」を明確にするだけで、いざというとき家族が助かります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 終活って何から始めればいいの?
A. 家族と5分だけ「将来どうしたいか」を話してみるのが第一歩です。
Q2. エンディングノートには何を書けばいいの?
A. 医療や介護の希望、財産の情報、家族へのメッセージなど、自分の気持ちをまとめて書きましょう。
Q3. デジタルの情報も整理する必要がある?
A. スマホやネット銀行、SNSの情報は「デジタル遺品」と呼ばれ、家族のためにも整理がおすすめです。
Q4. 写真や手紙など、思い出の品はどうすればいい?
A. デジタル化やスクラップブックにまとめて保管すると、気持ちもすっきりします。
Q5. 全部やりきれない気がします…
A. 一気にやらなくて大丈夫。「まずは1つ書いてみる」「1人と話す」など小さな一歩が大切です。